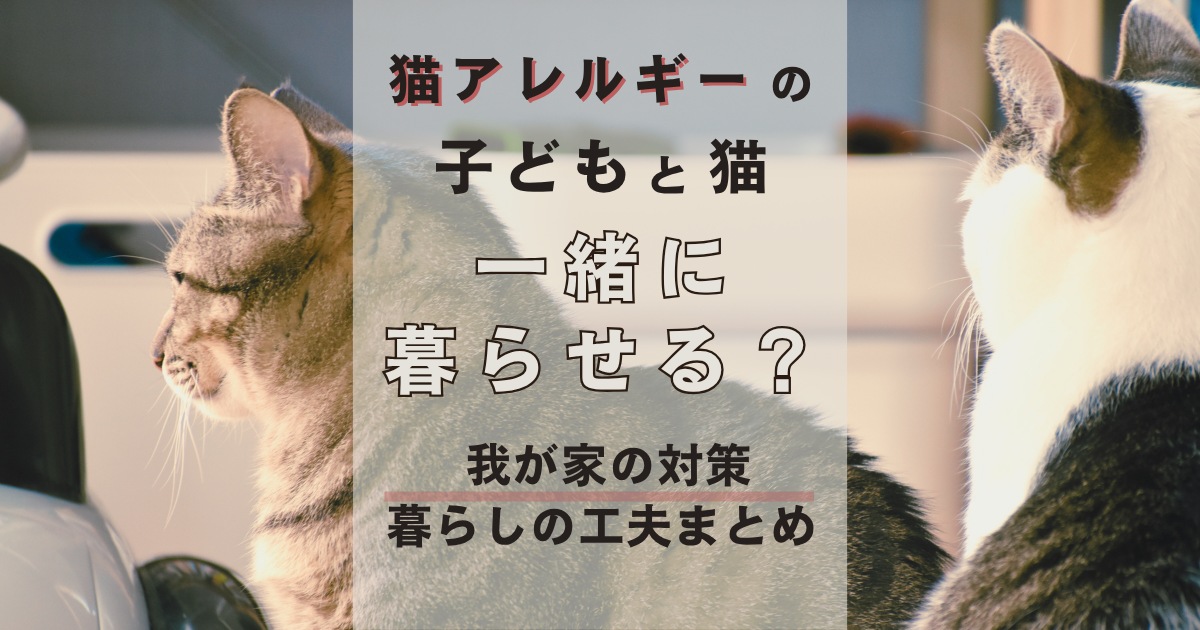「赤ちゃんが生まれるけど、猫がいるおうちはどうすればいい…?」
出産を控えて、そんな不安を感じるママは多いですよね。
我が家にも猫がいて、子どもと同じ空間で暮らしています。
そして、わが子は猫アレルギーです。
この記事では、そんな我が家で実践している「猫とアレルギー持ちの子供が共存するためにしていること」をご紹介します。
すでに猫と暮らしている方や、これから猫を迎えようか迷っている方に、少しでも安心してもらえたらうれしいです。
猫アレルギーの子どもと猫、一緒に暮らせる?
我が家では、子どもが赤ちゃんの頃から猫と暮らしています。

しかし、一緒に過ごしていると、「子どもが猫アレルギーかも…?」と、心配になることがよくありました。
実際に、猫アレルギーは子どもに多く見られる症状のひとつです。
うちの子の場合、3歳を過ぎた頃から、くしゃみや鼻水・目のかゆみが出るようになり、ひどいときには目の周りに赤みや蕁麻疹のような症状が出ることもありました。
病院で検査を受けた結果、猫アレルギーと診断されました。

や、やっぱり…!!!
では、猫アレルギーとはどんな症状があり、どう対処していけばいいのでしょうか?
猫アレルギーってどんな症状?
猫アレルギーの原因となる物質は、猫の毛そのものではなく「唾液」「皮脂」「フケ」などに含まれるたんぱく質です。
それが乾燥して空気中に舞い、吸い込んだり付着したりすることでアレルギー反応が起こります。
猫アレルギーの主な症状は、人によって出方に違いがありますが、以下のようなものが多く見られます。
まれに呼吸困難や血圧低下を伴うアナフィラキシーショックなど、命に関わる重い重い症状を引き起こす場合もあります。
そのため、症状が強いときや長引くときは、自己判断せず早めに医療機関を受診しましょう。
猫と安心して暮らすためには、まず正しい検査でアレルギーの程度を知ることが大切です。
アレルギーがあっても深まる猫との絆
猫アレルギーと聞くと、「猫との生活はもう無理かも…」と落ち込んでしまう方もいるかもしれません。
でも我が家の場合、症状をコントロールしながら、猫と一緒に暮らすことができています。
一部の研究では、乳児期に動物と接することでアレルギーになりにくくなるという説もあります。
ただし、すでに症状が出ている場合は、無理せず医師と相談しながら進めることが大切です。
赤ちゃんの頃から猫と過ごしていたことで、子どもは猫に対して一切の恐怖心がなく、むしろ小学生になった今では「いないとさみしい」と言うほど大好きです。
猫たちも、最初は遠くから様子を伺っていましたが、今では遊んでいるそばに寄り添ってくれるようになりました。

そもそも私は、猫と子どもが一緒に暮らすことに不安を感じていませんでした。
そして猫アレルギーと診断されたあとも、我が家の選択は「共存一択」
猫との絆は深く、共に暮らすための工夫をする価値があると、今も強く感じています。
猫アレルギーでも一緒に暮らすためにしたこと
猫との暮らしを続けるために、我が家ではいくつかの工夫をしてきました。
少しずつ積み重ねてきた対策を、ご紹介していきます。
子どもへの医師相談と薬の活用
我が子はもともと花粉アレルギーや軽度の喘息があるため、服薬は欠かせません。
症状に合わせて内服薬や点眼薬を処方してもらいました。
幸いなことに、猫と過ごしているときに喘息を起こしたことはなく、服薬を始めてからは喘息自体の発作もかなり減り、結果としてよかったです。
家族のルールと猫との距離感
猫と人が同じ空間で生活している以上、アレルゲンを完全に除去することは難しいです。
だからこそ、我が家では次の3つのルールを徹底しています。
猫と子どもが共存するために大切なこと
ルールは小さな積み重ねですが、猫との穏やかな暮らしにつながっています。
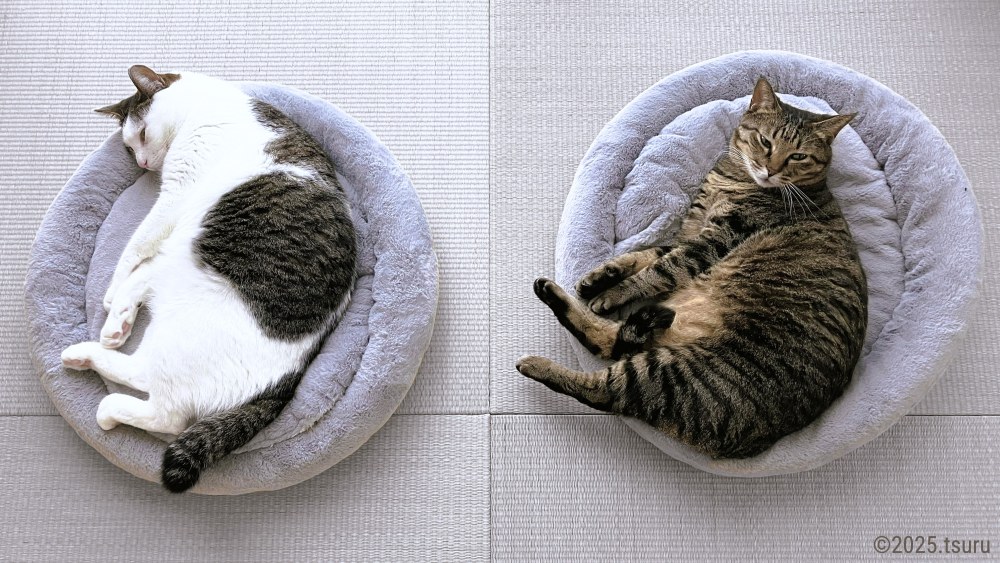
では、猫アレルギーの子どもと猫が一緒に暮らしていくために、どんな心構えや工夫が大切なのでしょうか。
ここでは、我が家の経験から感じた「猫と子どもが共存するための考え方」をまとめます。
「完璧」より「できる範囲」で
猫アレルギーがあっても、家族の一員である猫との生活をあきらめる必要はありません。
大切なのは、猫への愛情と、子どもの健康のバランスをどう取るかだと思います。
できることを無理のない範囲で続けていくこと。
我が家でも、掃除や手洗い、猫の居場所の工夫など、無理のないペースでできることを少しずつ続けてきました。
それでも症状が出ることはありますが、「一緒に暮らしたい」という気持ちがあるからこそ、前向きに向き合えているのだと思います。
家族みんなが安心できる環境づくり
猫との共存は、子どもだけでなく家族の協力があってこそ成り立ちます。
「猫は寝室に入れない」「お手入れは子どもがいない時間に」など、ルールもみんなで守るようにしています。
子ども自身も、猫と暮らすために必要なことを少しずつ理解し、手洗いや距離感を自然に意識するようになりました。
その姿を見ると、「一緒に暮らすって、こういうことなんだな」と感じます。

家族が安心して過ごせる環境を整えること。
それが、猫との絆を深めながら、一緒に暮らすための第一歩だと思っています。
猫と子ども、一緒に暮らしていくために
我が家では、医師との相談、生活環境の見直し、家族の協力を通して、猫との暮らしを続けてきました。
完璧を目指すのではなく「できる範囲でできることを続ける」「家族が笑顔で過ごせるペース」を見つけることが、大切だと感じています。
猫との暮らしは、子どもにとって癒しであり、とっても大切な時間。
アレルギー対策をしながら、家族みんなが心地よく過ごせるように、これからも工夫を続けていきたいと思います。
ちなみに、我が家で使っている猫用システムトイレについて、子育て家庭目線で詳しくレビューしています。
実際に使ってみた感想を、子育て家庭の視点でまとめましたので、よろしければこちらもご覧ください。
また、猫砂の種類によっても快適さは大きく変わります。
我が家で試したおすすめの猫砂を、使い心地や掃除のしやすさなどから比較しています。
猫との暮らしに不安を感じている方の背中を、少しでもそっと押すきっかけになりますように。